© Health and Global Policy Institute
歴史から紐解く日本の遠隔医療
佐藤 大介
本日はお忙しいところお時間をいただきありがとうございます。
遠隔医療の歴史は長いですが、数年前から政策や産業界において頻繁に登場する等、注目されている分野かと思います。
長谷川先生は遠隔医療協会や遠隔医療学会の理事としてご活躍です。ぜひ遠隔医療の歴史的経緯や現状、未来についてのお話を伺えればと思います。
――はじめに遠隔医療の定義と歴史的経緯についてお伺いしたいと思うのですが、「遠隔医療」という言葉はいつ頃から登場した言葉なのでしょうか。特に最近、新たに定義された「オンライン診療」という言葉もあり、一般の国民にとっては理解が難しい側面もあり、遠隔医療に関する政策のわかりにくさにつながっているように見えます。
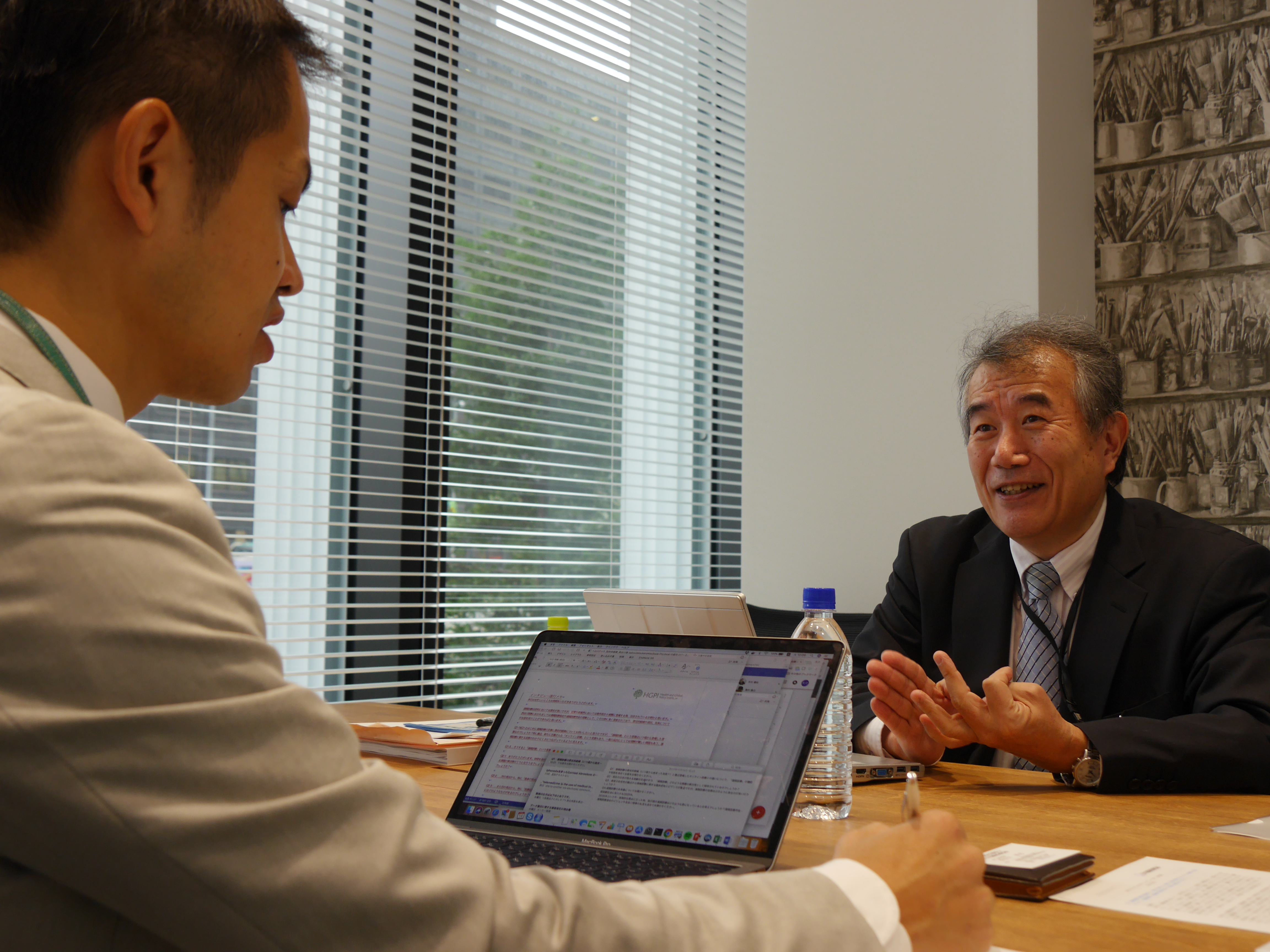
長谷川 高志
昨今は「遠隔医療」や「オンライン診療」と言われていますが、私は「オンライン診療」を「テレビ電話診療」という意味で「遠隔医療」と使い分けています。具体例を挙げると、たとえばネットワークに接続する血圧計やペースメーカーのデータを医療機関とつなげる方が「オンライン」だと思っていて、「オンライン診療」は対面診療の延長だと思っています。
まず「遠隔医療」の歴史的経緯についてですが、1990年代前半ぐらいにテレラジオロジー(遠隔放射線診断)が登場し、放射線から病理の領域に「遠隔医療」の機運が出てきました。ただ、現在であれば、光ファイバー通信で最大2000Mbpsの通信ができるところ、当時のテレビ電話(1990年代前半)はデジタル化された通信網(ISDN)の普及が広まりだした黎明期で、64kbpsの通信を高速と表現する時代でした。
当時は1回分の画像データを送るのに長い時間が掛かりました。このため、通信料金が安い時間帯である夜間にテレラジオロジーに関わる情報を送信する時代でした。こんな風に通信可能な情報量の制限があった頃に、テレビ電話なんて無理というか、いわゆる普及できる価格でテレビ電話診察は到底出来ないと考えられていました。当時、日本で早い時期にそれなりのテレビ電話診療を始めたのが1995年9月30日というのがありまして、おそらくこれが現在につながるプラットホームとしては一番初めだったのではないかと記憶しています。
当時の遠隔医療の研究は、内科医の研究者が主に関わっていたと思います。内科診断のツールを作れば遠隔でも内科診断ができ、自宅でも診療できるんだと考えられていました。そのため、診断機能をどれだけ高めるかが当時の遠隔医療のポイントだと思われていました。また、人間の感性を重視する研究だとも言うことが出来るかもしれません。血液マーカーや画像診断ではなく、聴診器で聞いた音も医師の感性を使って内科診断を行うという研究でした。当時から研究を続けている遠隔医療の研究者たちは、今でもこうした医師の感性による診断を重視する傾向があります。
また、これらの研究者は当時40歳前後くらいでしょうか。現在の新しい研究者たちとほぼ同年齢の頃に始めたのですが、当時はCTのスライスや画像は粗く、血液マーカーや虚血性心疾患や心筋症などの心臓不全状態の指標となる脳性ナトリウム利尿ペプチドを利用した、BNP(Brain Natriuretic Peptide)マーカーもありませんでした。現在では血液を採れば心機能も分かるしBNPマーカーは画期的な技術です。CT画像、血液マーカー、BNPマーカーを見るだけでも診察が成り立ちます。別の言い方をすれば、オンライン診療が成り立つのは、こうした診断技術の発展による要因も大きいと思ってます。別にだからといって今のオンライン診療は駄目だという意味ではなくて、実はそうした背景によって「オンライン診療」と「遠隔医療」という言葉が使い分けられているという意味です。
「オンライン診療」と「遠隔医療」の言葉を使い分けるもう一つの理由は、医者の文化の話なのですが、当時の遠隔医療と今のオンライン診療では求めるものが違います。当時は大きな科研費が取れる研究にするために、より高度な機能を工学的・医学的に求めてきました。そのため当時の遠隔医療は大学病院で診る診療行為が前提にあります。一方でオンライン診療は、診療所で診る診療行為という違いがあります。オンライン診療を批判する人の中には「診療所の医師は大学病院のような高度診療を行っていない」というようなことを言うのですが、それはこうした背景が関連していると思います。歴史的経緯や文化的背景の違いが、遠隔医療とオンライン診療の違いではないでしょうか。
また、当時の遠隔医療研究者は、自分の診察を一部でもいいから遠隔地でやりたいと希望していました。だから、当時は「遠隔診察」という言葉をよく好んで使っていたように思います。こうした歴史的背景を考えると遠隔診察、遠隔医療、オンライン診療と分類したほうがいいかもしれません。
もう1つ言葉を使い分ける他の理由としては、医療課題の違いがあると思います。当時の医療課題には在宅医療までは含まれていませんでした。そもそも1995年当時はまだ現在の定義である在宅医療自体が成り立つ以前でした。在宅医療が十分確立していない頃から医師法の解釈通知が併せて出たわけです。特に2003年の医師法の解釈通知は、在宅医療に関する診療報酬制度を全く想定してません。そのため当初の例示には「在宅アトピー」のような今から振り返ると違和感を感じる疾病名が載っています。
その後2008年前後に在宅医療がだんだん普及してきて、今の形の在宅医療に整ってきました。そのころに総務省の事業費により、ICTを利用して人口密度を薄いエリアをカバーする解決策として遠隔医療、テレビ電話診療を用いた事業も始まりました。医師・看護師・患者による遠隔医療、いわゆるD to N to P(Doctor to Nurse to Patient)という形態を生み出したのは、その頃に取り組んでいた新見市や山形県朝日町などでした。
佐藤 大介
――ありがとうございます。時間を現在に戻したいのですが、現在の日本が抱える高齢化社会の中で、「遠隔医療」は高齢化社会が抱える課題の解決策の1つとなりうるでしょうか。もし遠隔医療が解決策の1つになるのであればそれはどのような課題に対する解決策なのでしょうか。
長谷川 高志
現在の課題ですが、まずオンライン診療に関する1つ目の課題は、今のオンライン診療は問診程度で薬を処方するような診療については有効だと思います。これは男性型脱毛症(Androgenetic Alopecia: AGA)や漢方薬の領域で比較的多く実施されていると聞いたこともありますし、一理あると思っています。一方で、当初からの遠隔医療研究者にとっては取組の難しい研究課題だとは思います。これは大学病院の医師にとっては「薬だけの処方では医者不要」と思うのと似ています。
2つ目は自覚症状が少ない慢性疾患の治療の脱落防止です。ただ、単に忙しい人が通えない人の利便性というのは、どういった医療課題なのかがはっきりしません。
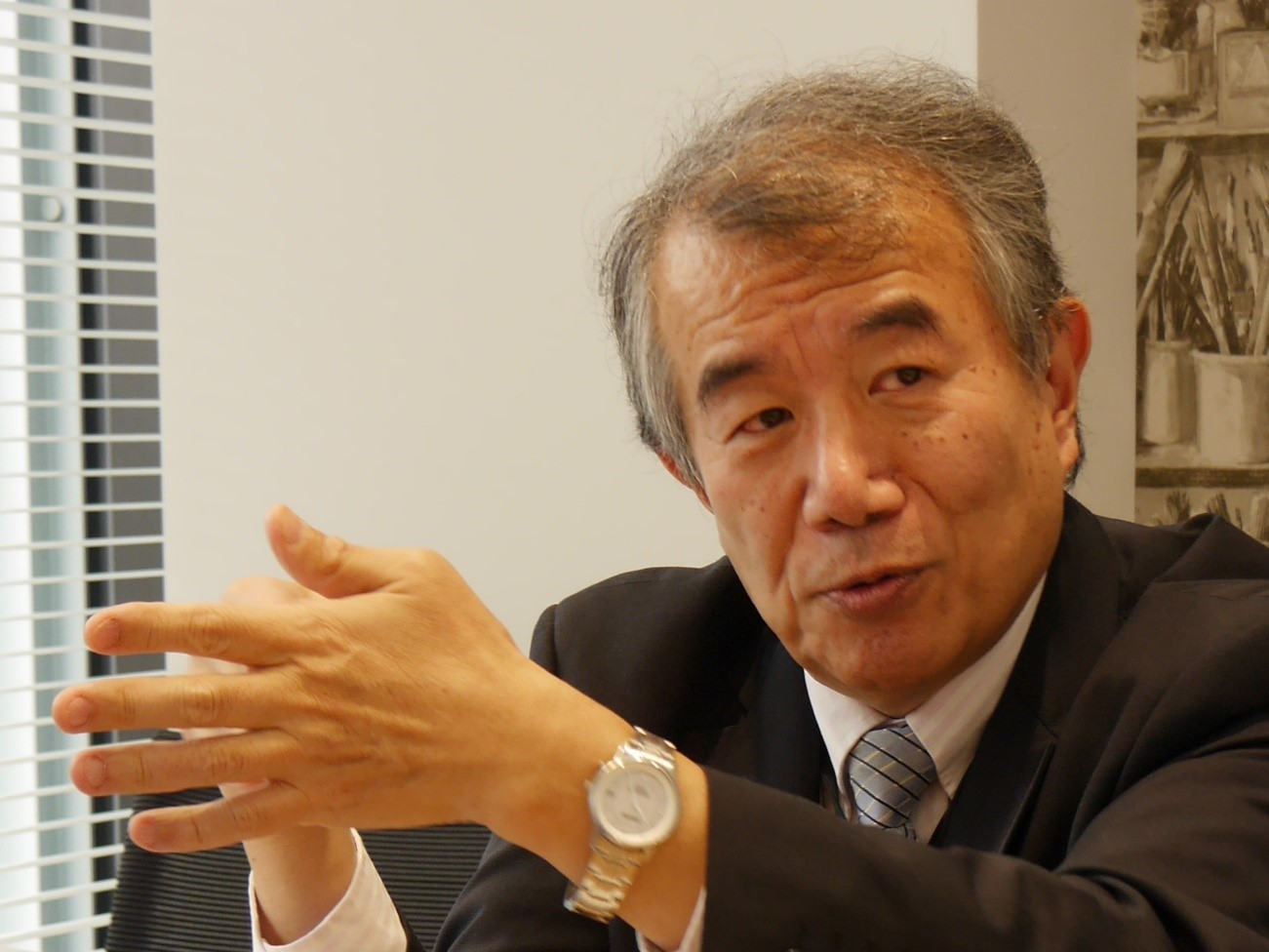
© Health and Global Policy Institute
3つ目は慢性疾患の治療から脱落させないという重症化予防の医療課題は重要ですが、これも当初からの遠隔医療研究者にとっては取組の難しい研究課題です。それは特定保健指導の保健師がやることだと関心を持たない医師がいるのと似ています。重症化予防は発症予防、軽い人が重くならないということですが、「軽い人だったら医者が診る問題ではなくて地域の保健指導の役割である」と思ってしまう、そういう医療の文化的な課題があるのも現実です。
現在の医療課題に対して、オンライン診療はすでにいくつかの分野で解決に取り組んでいます。たとえば認知症の人の日常管理とか、心療内科領域も出てきています。また、た、小児科において、疾病の緊急度等に応じて治療の順番を決めるトリアージについても地域の区とか市の保健福祉に関連した遠隔医療も始まっていると思います。特に在宅医療領域に一番取り組まれているのですが、オンライン診療にしろ遠隔医療にしろ、全体のプロトコル、もしくは治療計画であるクリティカルパスとして取り入れている領域です。たとえば訪問診療の計画書、在宅時医学総合管理料を請求する治療計画の中で、一部の訪問看護師が行っている部分を遠隔医療・オンライン診療を通じた医師の介入に置き換えるというものです。こうした慢性疾患や在宅医療における遠隔医療・オンライン診療の利活用は今後広まってくると思います。
オンライン診療も対象領域ごとに発展して次の形が出ると思います。オンライン診療自体がまだ未分化で、研究途上ではないかと思っています。在宅医療は遠隔医療に関する医療課題ですが、他にも幾つかの医療課題として利活用されるだろうという期待はあります。
別な医療課題として200床問題があります。200床以上の医療機関が遠隔医療を実施したい理由は2つあって、一つは地域のプライマリケア側のところを支援したい場合か、もう一つはその医療機関がへき地に位置しているという場合です。へき地の病院は在宅医療も担わなければならないこともあります。たとえば糖尿病は循環型クリティカルパスと呼ばれる連携パス、たとえば年間11回はかかりつけ医を受診し、年間1回だけ専門病院を受診するような医療機関と連携したクリニカルパスがあります。200床以上の病院が風邪や頭痛、高血圧の薬を処方するだけのような患者を診察する余裕はなく、より重症な患者へ医療資源を投入したいと思います。いわゆるクリニカルパスを決めて遠隔医療を用いるという在宅医療での使い方です。その場合、おそらく遠隔で外来を行う診療医が電話による外来診療料を全般的に認めるのではなくて、治療プログラムごとに外来診療料を算定可能にすべきとは思っています。つまり、オンライン診療も遠隔医療も治療プロトコルの一つだと思っています。
ある診療のためのクリティカルパスに対して、患者の状況や医療機関の機能によって、治療手段はいろいろ変わります。たとえばある人の場合は通院できるから外来にしてもらうとか、そのときの一つの道具として、テレビ電話やバイタルモニターもあるという選択肢が遠隔医療ではないでしょうか。
これらの議論から、オンライン診療についての診療報酬評価を考えると、簡単ではないと思います。たとえば「特に忙しい人のため」と言ってしまうと医療課題がぼやけてしまいます。また、一歩間違えるとブラック企業を助長しかねません。「私は忙しくて医者へ行けないですよ」って、ブラック企業に勤めてる人をさらに酷使する集団のために保険医療サービスを使ってよいのでしょうか。いずれにせよ、オンラインであれ、オフラインであれ、医療課題とならない問題を数多くあるデータの中から意図的に一部のデータを用いて議論を誘導しようとするチャンピオンデータを用いて導き出された答えのままでは溝は深いままだと思います。
佐藤 大介
――ありがとうございます。おそらく地域包括ケアの医療提供体制そのものを考える上で、遠隔医療あるいはプロトコルを評価することが重要になると思うのですけど、これらのエビデンス(論拠)をどう測るのかが難しい課題と思うのですが、その点はいかがでしょうか。

© Health and Global Policy Institute
長谷川 高志
たとえば岩手県で調査をする機会が多く、各地を見せていただきましたので、遠隔医療の政策研究として良いフィールドだと思っています。しかしながら、まだエビデンス自体は少ないです。加えて地域医療計画として遠隔医療を考える場合、その地域にどんな年齢層や病気を持つ住民がいて、医療機関や医療スタッフが供給できる体制があるのか。それに対して遠隔医療を活用するとどれだけ供給量を増やすことができるか、というエビデンスが少ないです。今一番不足しているのはこういう社会的エビデンスで、遠隔医療の必要性が不明瞭です。エビデンスと言うと臨床エビデンスを指して、有効性があれば診療報酬が付くと信じられていますが、有効性を出しても診療報酬での評価は難しいと思います。たとえば、オンライン診療を在宅で使って有効というエビデンスを出したとします。
一方で、肺がんなどにおいて、がん細胞が縮小もしくは消滅した患者の割合を用いて治療の経過を判断する奏効率40パーセントの画期的な抗がん剤が開発されたとします。保険収載としてどちらを取りますかと言ったら、私は肺がん患者さんを救ったほうが良いと言うかもしれません。もし奏効率40パーセントの抗がん剤を利用できる対象者は実は全人口の1パーセント以下で、それに対して、遠隔医療で救える患者の数はもっと多いですと判れば遠隔医療を取ります。要するに、社会的エビデンスがもっと必要なのだと思います。
臨床エビデンスについてはCPAP(シーパップ)として知られている、持続式陽圧呼吸療法(CPAP: Continuous Positive Airway Pressure)や心臓ペースメーカーについては、遠隔医療でフォローすることで、外来を受診する頻度が下がったり、診療間隔が長くなっても有害事象発生率が変わらないというエビデンスはあります。もし遠隔医療で患者の状態をモニタリングした結果を踏まえた医師による指導により、さらに結果も改善したエビデンスがあれば、新たな加算の可能性が出てくるかもしれません。いずれにしても遠隔医療の臨床研究や社会科学研究のデザインを考える研究グループが必要に思います。
佐藤 大介
――ありがとうございます。
最後に遠隔診療の未来についてお伺いいたします。地域医療構想の目標の年である2025年、あるいは保健医療2035として中長期的将来という位置づけられている2035年、遠隔診療の未来はどうなってるのでしょうか。
長谷川 高志
2025年の段階でも遠隔医療は不完全かもしれません。遠隔医療はこれまで話した通り様々な考え方や視点がありますが、医療提供体制の課題そのものと密接にかかわると思っています。にもかかわらず遠隔医療を地域包括ケアとして取り組んでいる人材が少ないと危惧しています。特にこの分野では医療政策研究者が少ないと思います。
そういう意味では、遠隔医療学会としても研究者がもっと増えて欲しいし、あるいは遠隔医療やヘルスケアICTに興味を持って欲しいという想いがあります。
遠隔医療やICT医療の未来は、アマゾンジャパン合同会社の運営するECサイトである、Amazon.co.jpをイメージするとわかりやすいと思います。Amazonが他社より強いのは技術そのものだけではないでしょう。

© Health and Global Policy Institute
商品検索、受発注、決済、物流をうまく組み合わせたからできたのだと思います。最近の遠隔診療の議論は受発注システムだけを取り上げてAmazonすべてを評価するような議論です。こんなに素晴らしい受発注システムを作ったから医療は変わります、と言われても、決済は?配送は?という問題は取り上げられません。受発注システムだけを取り上げて全体を議論しているうちは、20年前ぐらいの企業の情報システム部というか、遠隔医療も一歩間違えると同じ状況に陥る可能性があるので、あらためて最高技術責任者(CTO: Chief Technical Officer)のような人材が求められていると思います。地域包括ケア等の医療提供体制全体を俯瞰できて、かつ運用としてのAからZまでICTを使って一気通貫で考えられるチームで、さらにいえば、地域の保健福祉部に強力な企画担当の長が必要だと思います。
これらの課題はおそらく日本の社会医学系学会全体が考えなくてはいけないテーマだと思います。個々の学会は専門家ですが、社会全体を動かすための人材育成が重要な課題に思います。

